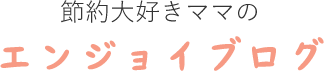子どものスマホ依存が心配
ショッピングやインターネットバンキングなど、スマホ一台さえあれば外出しなくてもさまざまな作業をこなせる便利な時代になりました。
外出する際にも、スマホさえ持っていれば現金やお財布を持って行く必要もないため、どうしてもスマホに依存しがちです。
スマホに依存するのは大人だけではなく、子どもも同じです。
ただ、子どもの場合にはスマホに依存するあまり、勉強がおろそかになったり近所の子どもと遊ぶ機会が少なくなったりといった弊害が心配されます。
スマホで何をやっているかを24時間監視するわけにもいかず、かといってスマホの使用を全面的に禁止するわけにもいかず、親としては心配が増えるばかりです。
子どものスマホ依存がひどくなってくると、宿題をしなくなるばかりか睡眠の時間を削ってスマホに熱中してしまうことがあります。
中にはアプリゲームにはまってしまい、高額の請求に親が頭を悩ませるケースも多くなってきていいます。
スマホ依存をやめさせるには
スマホは確かに便利な道具ですが、程度を過ぎるとスマホなしでは落ち着かなくなり、日常生活にも支障をきたしてしまうことさえあります。
スマホに依存しやすい子どもは精神的に弱い、あるいは家庭環境に問題があるといったトラブルを抱えている傾向が多いものです。
学校の勉強についていけずにストレスを感じている子どももスマホに依存しがちです。
スマホを見ている時間が増えると、ドライアイや視力の低下などを目のトラブルに見舞われることがありますし、肩こりや神経系の不調などといった問題が出てくることもあります。
ひどい場合には自律神経失調によるめまいや吐き気を訴える子供もいますし、スマホ首などの問題も心配です。
スマホ首はストレートネックとも呼ばれており、背中や首に常に負担をかけた状態になりますので、姿勢が歪んでくることも心配されます。
SNSで友達と連絡を取り合うなど、今やスマホは親にとっても子どもにとってもなくてはならない存在ですが、完全に依存するのを防ぐためにはスマホの使用時間を制限することも大切です。
スマホを使用できるのは1日に2時間以内、あるいは学校に行く前は15分間だけ、午後は1時間だけといったように使用時間を決めるようにするといいでしょう。
スマホ依存症対策アプリもおすすめ
スマホのアプリの中には「スマホ依存症対策 アプリ」というものもあり、インストールすることによってスマホが使えなくなりますので、上手に活用するのもいいかもしれません。
いろいろと対策を講じても効果がない場合には、小児科や心療内科クリニックで相談をしてみるのもおすすめです。
さらに、学校のスクールカウンセラーなどに相談するのも効果があります。